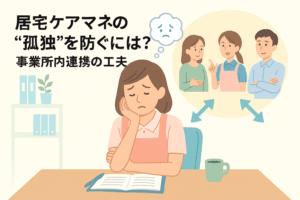
居宅介護支援事業所で働くケアマネジャー(介護支援専門員)は、利用者や家族、医療・介護関係者との調整役として日々多忙を極めています。
そんな中、「孤独を感じる」「誰にも相談できない」といった声が現場から聞こえてくることも少なくありません。
ケアマネジャーの孤立は、業務の質や継続性に影響を及ぼす可能性があるため、事業所内での連携やメンタルケアの仕組みづくりがますます重要になっています。
1. 情報共有の仕組みを整える
ケアマネジャーは個別支援に関わるため、業務が属人的になりやすい傾向があります。
そこで、定期的なミーティングやケース検討会の開催が有効です。
・他のスタッフとの意見交換により、視野が広がる
・難しいケースへの対応方針を共有できる
・業務の属人化を防ぎ、チームとしての一体感が生まれる
また、電子カルテや共有フォルダの活用により、情報の透明性とアクセス性を高めることも効果的です。
2. メンタルケアの意識を高める
ケアマネジャーは、利用者の人生に深く関わる仕事であるがゆえに、精神的な負担も大きくなりがちです。
事業所として、メンタルヘルスに配慮した取り組みを行うことが求められます。
・定期的な個別面談で心の状態を確認する
・ストレスチェックや外部相談窓口の案内
・「話せる場」「休める時間」の確保
こうした取り組みは、離職防止にもつながり、長く働ける環境づくりに寄与します。
3. “相談できる関係性”を育てる
制度や仕組みだけでなく、人間関係の構築も孤独を防ぐ鍵です。
日常的な声かけや雑談、ちょっとした気遣いが、心理的安全性を高めます。
・上司や同僚が「いつでも相談していいよ」と伝える
・新人ケアマネへのフォロー体制を整える
・感謝やねぎらいの言葉を交わす文化を育てる
こうした関係性があることで、困難な場面でも「一人じゃない」と感じられるようになります。
まとめ:孤独を防ぐことは、質の高い支援につながる
ケアマネジャーが孤立せず、安心して働ける環境を整えることは、利用者への支援の質を高めることにも直結します。
事業所内での連携やメンタルケアの工夫は、チーム全体の力を引き出すための土台です。
もし「自分の事業所ではどうすればいいのか」「具体的な仕組みづくりに悩んでいる」と感じたら、専門家への相談を通じて、客観的な視点や実践的なアドバイスを得ることも一つの方法です。





